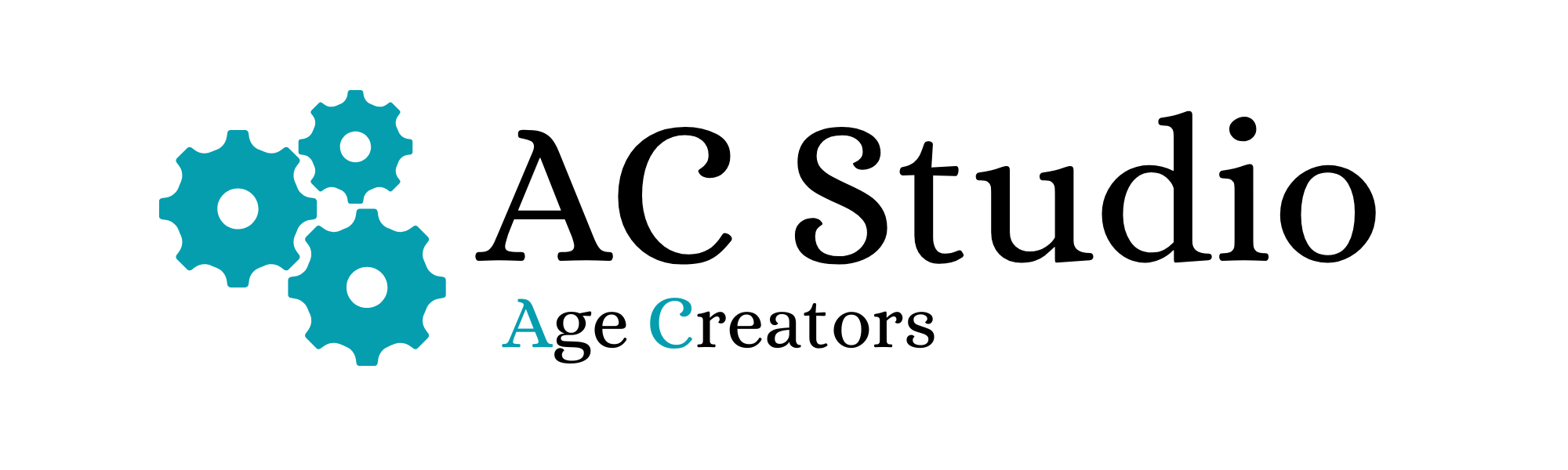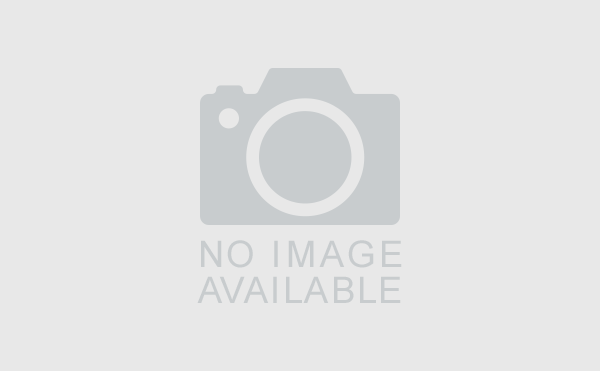大阪・関西万博の培養肉展示は何を示したのか
――世界の制度・市場動向と併せて読む
1. 事実:大阪・関西万博で何が展示されているか
- 展示主体と場所
大阪・関西万博(2025年4月13日〜10月13日)の大阪ヘルスケアパビリオン「ミライの都市」エリアにて、培養肉未来創造コンソーシアム(大阪大学、島津製作所、伊藤ハム米久HD、TOPPAN、シグマクシス、ZACROS)が「家庭で作る霜降り肉」というブース名で出展。実物の培養肉とミートメーカー(家庭用を想定したコンセプト機)を公開。 - 展示の主旨
「お肉は店で買うものから、家庭で作るものへ」という未来像を提示。3Dバイオプリンティングを含む製法・評価技術の紹介と、個人の嗜好や栄養設計に合わせた霜降りを生成するというビジョンを示す。 - 世界初の主張について
これまでに一般向けの展示・提供は他国でも実施(例:シンガポールでの販売開始、米国での限定提供)。したがって大阪万博の展示は「日本での大規模一般展示として先進的」と表現するのが正確。
2. 主要地域の制度・市場の最新状況
2-1. 先行承認・提供の実績
- シンガポール:2020年以降、培養チキンの商業提供を段階的に承認・実施。
- 米国:2023年6月、UPSIDE FoodsとGOOD Meatの培養チキンがFDA/USDAのプロセスを完了し販売可に。限定提供の事例あり。
- イスラエル:2024年1月、Aleph Farmsの培養ビーフステーキに対し世界初の牛肉の規制承認。
2-2. 欧州の動向(分化)
- 承認ステータス:EU域内でヒト用の培養肉は未承認(2025年時点)。一方で英国はペットフード向け培養チキンを承認し、2025年2月に世界初の店頭販売が実施された。
- 規制・表示:
- イタリアは2023年12月、培養肉の生産・販売を禁止する法律を施行。
- フランスは植物肉の「肉的表現」禁止を模索したが、EU司法裁判所判断などで揺れる状況。
2-3. 中東(食料安全保障の文脈)
- イスラエルは前述のとおり承認・商用化準備を進行。UAEや湾岸諸国は投資・規制検討を活発化(UAEでの承認は未確認、ただし参入意欲が強い)。
2-4. アフリカ(拠点化の兆し)
- 南アフリカ:Mzansi Meat/Mogale Meat/Newform Foodsなど複数社が研究・実証を推進。Newform Foodsは低コスト実証設備計画を公表。
- 消費者受容:過去の調査では、若年層の受容が比較的高い傾向を示す報告あり(例:若年層での購入意向が過半のデータ)。ただし調査年・対象の違いに留意が必要。
2-5. その他の動向(米国内の規制揺り戻し)
- 米国の一部州では培養肉販売禁止・学校給食での制限などの逆風も発生しており、連邦承認と州法の齟齬が課題。
3. 考察
- 研究から社会実装への「可視化」
大阪・関西万博の展示は、製品としての市販・喫食まで踏み込むものではない一方で、作る肉という体験価値を生活者目線で可視化した点が大きい。これは制度整備・サプライチェーン整備・コスト構造改善に向けた社会的合意形成を後押しする。 - 地域ごとに異なる「推進理由」
先進国(環境負荷・動物福祉・技術主導)と、新興国(食料安全保障・タンパク質不足・経済多角化)では推進のロジックが異なる。この非対称性は市場投入の順序や価格設計、用途(ヒト用/ペット用)に影響する。 - 規制の二層化と市場の段階導入
英国のペットフード先行は、安全性・社会受容を段階的に積み上げる戦略として合理的。ヒト用の本格量産・価格低下前に「用途別に足場を築く」動きは他地域にも広がる可能性。 - 日本のポジション
日本は展示・周知で先進的であり、評価技術・素材(培地・足場材)・プリント技術など周辺技術の国際分業で存在感を高めうる。並行して国内の制度設計(安全性審査・表示・衛生管理)とサプライチェーンの議論が要る。
一方で、技術力とともに、培養肉が家庭に溶け込む世界観を提示することで、同分野での先進性と、新たな暮らし方の提案という未来構想力も世界に示すことができている。
4. 現状認識の総括
- 大阪・関西万博の培養肉展示は、日本での大規模一般展示として先進的で、実物展示+家庭用コンセプト機により作る肉という未来像を社会に提示した。
- 世界では、シンガポールと米国が人向けで業界をリードしており先行国という位置付け。イスラエルが牛肉で世界初の承認を実現。欧州は未承認だが英国はペットフードで突破口、一方でイタリアの禁止など規制は分化。南アフリカは事業基盤と若年層の相対的受容でアフリカ拠点化の兆し。
- 次の論点は、コスト・スケールアップ・制度調和・表示・供給用途の段階設計であり、日本の強み(周辺技術群)を活かした国際連携が鍵。
5.参考:今後の展望
今のところ、本格的な普及までにはまだ数年単位で時間がかかる見込みです。以下は上記をインプットとしたときのAI(chatGPT)による展望です。参考までに。
短期(〜2027年)
- 人向けはシンガポール・米国・イスラエルで承認済みだが、販売は限定的・外食や試験販売レベル。
- 市場拡大の先頭はペットフード。英国で2025年から一般販売が始まり、他国も追随する見込み。
- 規制は国や州ごとに分断(イタリアなど禁止国、米国でも一部州が制限)。
- 量産コスト(培地、バイオリアクター)が高く、採算が合わないため、大規模流通までは時間が必要。
中期(2028〜2032年)
- 培地コスト削減(成長因子の代替・リサイクル)や大容量バイオリアクターの稼働が進み、業務用・外食・加工食品向けに定常的な利用が始まる可能性。
- 価格は依然として畜産肉より高いが、**ミンチやハイブリッド製品(植物+培養)**は一部で採用が進む。
長期(〜2035年)
- BCGなどの予測では、代替たんぱく市場全体の11〜22%を占めるとの見込み。その中で培養肉は数%程度を構成するとの予測が主流。
- 完全な価格同等化は一部製品に限り2030年代に入り実現する可能性。
- 普及の順序は、ペット → 加工・業務用 → 高付加価値外食 → 家庭向けの段階的拡大が現実的。
今後の展望のまとめ
- あと数年は技術・規制・価格が足かせとなり、急速な拡大は難しい。
- 2030年前後に加工・外食分野で実用段階へ進み、2035年頃には特定カテゴリーで価格同等化し普及が進む可能性。
- 日本は展示・周知では先進的で、培養肉そのものよりも評価技術や培地・プリンティング材料など周辺技術の国際展開に早期から貢献できる。
→ 結論:商業的な拡大はまだ時間を要しますが、2030年代前半には業務用・加工用途を中心に着実に市場が立ち上がるシナリオが現実的です。
参考URL(一次情報・公的資料・主要メディア)
- 大阪・関西万博/展示概要:
- Shimadzu(展示告知)https://www.shimadzu.com/news/2025/duxtpaihorp0fll8.html
- Shimadzu Today(展示紹介)https://www.shimadzu.com/today/20250526-1.html
- CFICM(公式)https://cficm.jp/en/
- TOPPAN(展示案内)https://www.holdings.toppan.com/en/news/2025/04/newsrelease250407_2.html
- 先行承認・提供:
- 米国(Reuters)https://www.reuters.com/business/retail-consumer/upside-foods-good-meat-receive-final-usda-approval-sell-cultivated-meat-2023-06-21/
- UPSIDE公式 https://upsidefoods.com/blog/upside-is-approved-for-sale-in-the-us-heres-what-you-need-to-know
- シンガポール(Food & Wine)https://www.foodandwine.com/news/lab-grown-meat-first-restaurant
- イスラエル保健省 https://www.gov.il/en/pages/17012024-02
- 欧州の制度状況:
- 英国(ペットフード承認・世界初販売)
- アフリカ(南アフリカ中心):
- 米国内の逆風(州法)
今後の予測に関するエビデンス記事)
・GFI「State of the Industry: Cultivated Meat 2025」
https://gfi.org/resource/cultivated-meat-seafood-and-ingredients-state-of-the-industry/
・BCG & Blue Horizon「The Protein Transformation」
https://www.bcg.com/publications/2021/the-benefits-of-plant-based-meats
・英国での培養肉ペットフード販売
https://www.theguardian.com/environment/2025/feb/06/uk-pets-at-home-world-first-lab-grown-meat-dog-treats
・米国承認(UPSIDE, GOOD Meat)
https://www.reuters.com/business/retail-consumer/upside-foods-good-meat-receive-final-usda-approval-sell-cultivated-meat-2023-06-21/