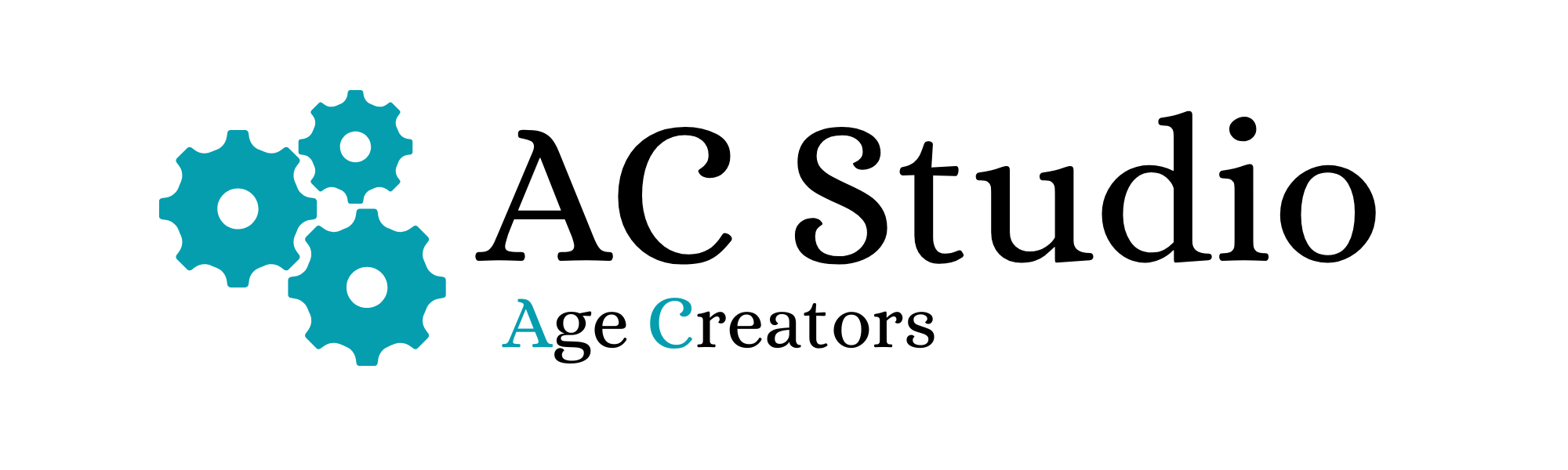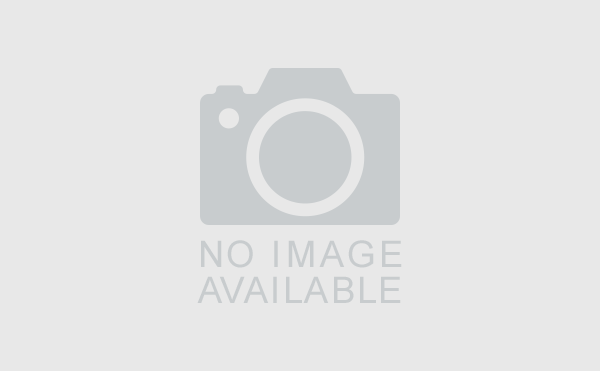中国・世界の再生可能エネルギー、実はここまで来ている―事実を直視し「やらない理由」ではなく「やる気概」を!
はじめに:見過ごされがちな世界の現在地
2025年、再生可能エネルギー(再エネ)の拡大は量も速度も歴史的な局面を迎えています。
なかでも中国の導入規模と成長速度は、国際機関や主要報道の一次情報を突き合わせると桁違いです。
日本では断片的な報道にとどまり、この現実を知る人は多くありません。
しかし、温暖化対策と産業競争力の両面から、まずは事実を正確に把握することが不可欠です。
1. 中国の再エネ拡大:2025年の現実
圧倒的な設備容量
中国国家エネルギー局(NEA)の最新統計によれば、
2025年8月末の時点で太陽光は1.12TW(1,120GW)、風力は0.58TW(580GW)、総発電設備は3.69TWで前年同期比18%増でした。
上半期(1〜6月)だけで新たに接続された発電設備は268GW、そのうち91.5%が再エネです。
内訳は太陽光212GW、風力51GWで、再エネ発電量は約1.8兆kWhに達し、全国総発電量の39.7%を占めました。
さらに、2025年3月末には風力と太陽光の合計容量が1.48TWに達し、初めて火力発電を上回りました。6月末には1.67TWに拡大しています。
地域別の展開:西部の巨大基地と沿海の分散型
- 内モンゴル自治区では、2025年5月末で再エネ設備が143GWに到達し、2025年は40GWの新規接続を目標に掲げています。
- 新疆ウイグル自治区は、2025年7月末で総設備容量219GW、うち再エネ128GW(比率60%)を占めています。
- こうした西部の超大型基地とともに、東部・沿海部では分散型太陽光や洋上風力の拡大が進んでいます。
蓄電と市場改革
急速な再エネ導入を支えているのが新型蓄電(リチウムイオン・フロー電池など)です。
稼働容量は2024年末で73.8GW/168GWh、2025年6月末には94.9GW/222GWhへ半年で29%増。
国家目標では2027年に180GWまで増強する計画です。
さらに2025年6月から新規の風力・太陽光は売電価格を市場ベースに移行。
補助金主導から市場駆動への転換が始まりました。
これに伴いグリーン電力証書(GEC)の取引量も急増しています。
2. 他国との比較:スケールの違いは歴然
世界主要地域の累積導入量を比べると、次のようになります(2024年末〜2025年中期データ)。
- 太陽光(PV)
- 中国:1,120GW
- 米国:236GW
- インド:123GW
- EU(参考):約338GW
→ 中国は米国の約4.7倍、インドの約9.1倍
- 風力
- 中国:580GW
- EU-27:236GW
- 欧州全体:291GW
- 米国:150GW台
→ 中国はEU-27の約2.5倍、米国の約3.7倍
また、2025年上半期だけで中国は268GWの再エネを新設し、その規模は他地域の年間追加量を上回っています。
3. 構造的な特徴
- 量のスケールが突出:単年で世界の増加分に匹敵
- 電源構成の転換:再エネ比率が発電量ベースで約4割へ
- 西発東送を支える送電・蓄電:内陸の巨大基地と沿海部の需要地を結ぶ超高圧送電線と急増する蓄電設備
- 制度改革の推進:補助金から市場取引へ移行しつつ、GECや省間取引を拡充
4. 日本では十分に知られていない事実
日本国内では、こうした中国の圧倒的な規模とスピードはほとんど報じられていません。
注目はむしろ電力価格やAI向けの電力供給などの課題に向けられ、どこかの国に忖度してか、この再エネ急伸という潮流は実感をもって共有されていないのが現状です。
5. 考察:日本は「やらない理由」ではなく「やる気概」を
(1) 世界の共通課題としての温暖化対策
温暖化を止めることは、人類全体にとって避けられない課題です。その状況は加速度的に悪化しています。それにも関わらずアメリカは温暖化よりもAI・テクノロジー、それに流されて各国の対策もトーンダウンしています。本当は、加速しなければいけない状況なのに。そして、心な中ではそれに気付いているのに。
「他国がやらないから自国もやらなくていい」という発想は、もはや成り立ちません。
今後、温暖化が進み、異常気象や、砂漠化、海面上昇、農業、水産業への影響、生態系への影響なども加速していきます。それが表面化するにつれ、、世界の潮流は確実に再エネ主導へと傾くはずです。
AIが進んで、なんとかしてくれるという楽観論は、AIが解決してくれる兆しが出てからやれば良い、それまでは全力で取り組むべき課題であるはずです。
(2) 経済競争力と安全保障の視点
再エネ拡大は単なる環境対応ではなく、次世代の産業基盤でもあります。
安価で大量に供給される中国の太陽光パネルや蓄電池は、世界市場の価格を下げ、再エネの普及を後押ししています。
日本にとっても、エネルギーの自給性向上・調達コスト低減・地政学リスク分散など多くの戦略的メリットがあります。
これを活かさずに遅れを取れば、産業競争力そのものを失いかねません。
(3) 日本が強みを発揮できる領域
日本はかつて省エネ技術や高効率機器で世界をリードしてきました。
再エネの主役はすでに中国が握っていますが、まだまだ革新的な技術は望まれますし、その覇権争いはこれからです。
- ペロブスカイト太陽電池
- 蓄電池の寿命・安全性・リサイクル
- 需給予測とデマンドレスポンス(AIによる最適制御)
- 地域マイクログリッド、災害対応型の分散電源
- 再エネ由来のグリーン水素と産業用熱の電化
- 送配電網のデジタル制御・市場設計
などなど、日本が技術・制度で貢献できる分野は沢山あるはずです。
(4) 社会としての意識転換
再エネ拡大は、「義務」だけでなく「成長の機会」です。
地域での新産業創出、雇用拡大、地方経済の活性化にもつながります。
逆に、化石燃料依存を長引かせれば、エネルギー価格の変動や国際的な規制コストに振り回されるリスクが高まります。
今必要なのは、「やらない理由」ではなく「やる意義と気概」です。
他国の動きに追随するだけでなく、自国の強みを活かし世界をリードする分野を明確に打ち出すべきでしょう。
そのために、まず世界の事実を直視すること。
そして、特定の国に忖度している場合ではありません。
できるだけ早く、次世代産業を育てる成長戦略・ビジョンを掲げ、産官学民があらゆる領域で行動する。
そのことこそが日本の将来の競争力を創造する道になるのではないでしょうか?
参考URL(出典一覧)
- 中国国家エネルギー局(NEA)
- 新華社(Xinhua)「China's installed power generation capacity up 18 pct」(2025年9月26日)
- People’s Daily Online「Renewable energy on fast lane」(2025年7月31日)
- China Daily「Renewable energy capacity up in H1」(2025年8月1日)
- Global Times「Wind + PV surpass thermal power」(2025年3月・6月)
- China Daily(内モンゴル・新疆の地域報道, 2025年)
- Global Energy Monitor「China’s solar & onshore wind update」(2025年5月)
- People’s Daily「China leads the world in new-type energy storage」(2025年9月)
- EnergyTrend「New-type Energy Storage 94.91GW/222GWh」(2025年8月)
- 国務院「新型蓄電 三カ年行動計画(2025–2027年)」
- pv magazine「China to switch from FITs to market-oriented renewables pricing」(2025年2月)
- Carbon Brief「Explainer: China’s renewable pricing reforms」(2025年2月)
- People’s Daily「GEC発行・取引の急増」(2025年春)
- Reuters「China’s coal additions surge in H1 2025」(2025年8月)
- SEIA / NREL「Spring 2025 Solar Industry Update(2024年末累計236GWdc)」
- WindEurope「Latest wind energy data for Europe(2025年秋)」
- MNRE(インド再生可能エネルギー省, 2025年8月)