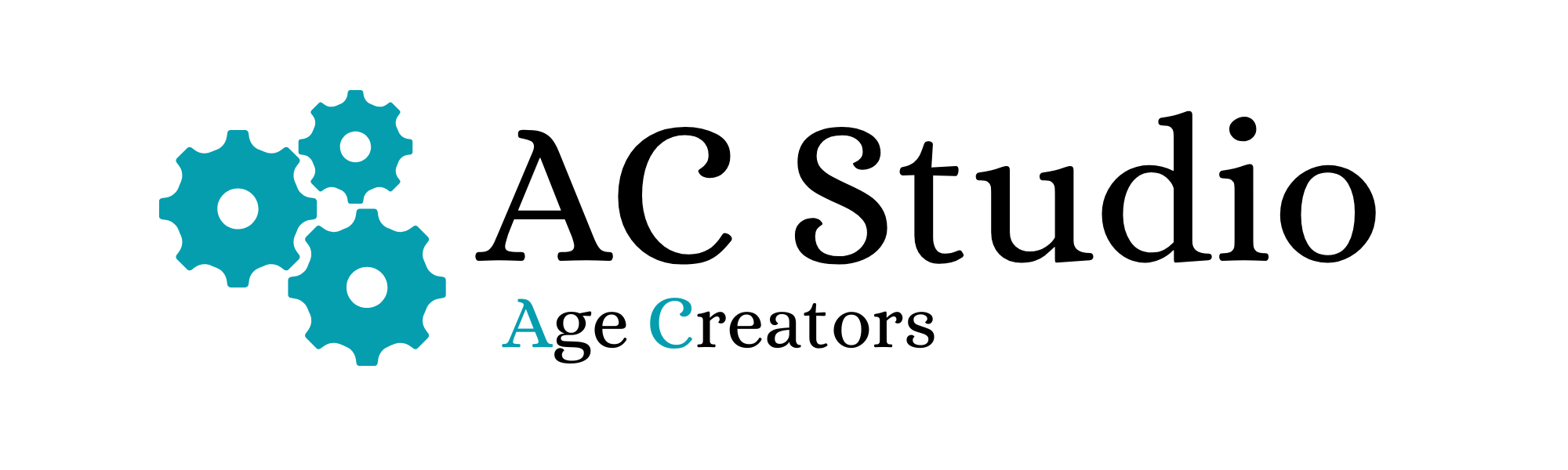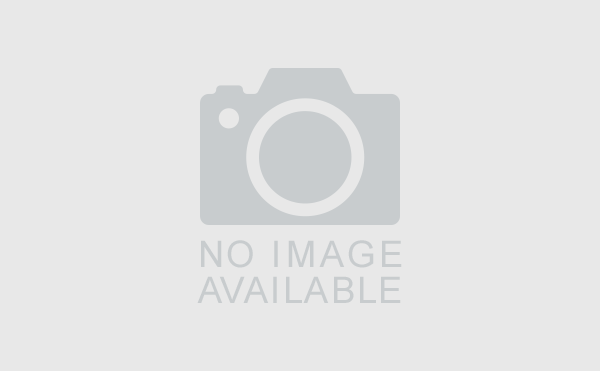気候変動の時代に広がる新しい食の動き「Climavore」とは何なのか?
はじめに
「何を食べるか」で、海や土や生きものとの関係は変わります。
Climavore(クライマボァ)は、気候変動の現実に合わせて食を選び直す考えと、その実践を広げる動きです。アート、建築、エコロジー、地政学などの境界をまたぎながら、食を通じて社会の仕組みを見直す——そんなプロジェクトとして2015年にイギリスで始まりました。
この記事では、海外で何が起きているのかを事実に基づいて紹介し、そのうえで日本での報道がなぜ少ないのかを考えます。
いま海外で起きていること
1) 何をしているのか(主な活動内容)
Climavoreは、展示やインスタレーション、パフォーマンス、映像、地域連携、レストランのメニュー改変など、実践を伴う形で広がっています。代表例は「潮が引くとテーブルになり、満ちると海のすみかに戻る」ように設計された潮間帯の食卓。海藻や貝など、海をきれいにし、生きものの居場所を増やす食材を使い、食と生態系のつながりを体で感じられるようにします。
また、ロンドンの王立芸術大学(RCA)とコミュニティ・ジャミールと組んだ研究プログラムでは、湿地や乾燥地での「食のあり方」を、地域の人々・料理人・研究者と一緒に学び、試し、形にしています。たとえば、湿地の再生と乳製品文化をつなぐ試みや、単一作物に偏った農法を見直す種子プロジェクトなどです。
2) どこまで広がっているのか(ムーブメントの規模)
- 美術館・文化施設との連携
イギリス各地の美術館・博物館のカフェやレストランが「Becoming CLIMAVORE」というネットワークに参加し、養殖サーモンをメニューから外すことを起点に、海藻・貝類・海の野菜など、海を回復させる食材へ置き換えています。参加施設には、ヴィクトリア&アルバート博物館(V&A)、サイエンス・ミュージアム、BFIサウスバンク、テート各館、マンチェスター・アートギャラリー、ホルバーン・ミュージアム、王立植物園(エジンバラ)など、英国を代表する文化施設が並びます。イギリス国内だけでも20館以上が参加し、21館が養殖サーモンを外したとする記録もあります。 - 国際的な広がり
2025年1月には、デンマークのMAPS(Museum of Art in Public Spaces)が、この国で初めての参加館になりました。イギリス発の動きが、北欧をはじめ海外にも波及しています。 - 食品サービス企業との協働
英国の大手フードサービス企業 Benugo は、文化施設の飲食運営と連動し、メニューの見直しや新商品の開発など、実務面から移行を支えています。
要するに、Climavoreは「アート×食×生態系」の交差点からはじまり、文化施設という公共の食の入り口を通じて、ゆっくりと現実のメニューを変えているのです。
3) 何が新しいのか(着眼点)
- 固定の禁止リストではなく、状況に合わせて変える
「いつもこれを食べよ/食べるな」という固定ルールではなく、地域や季節、海や土の状態を見て、最適な食材をその都度選ぶという考えです。 - 食材が環境の回復に効くこと
海藻や二枚貝(ムール貝・カキなど)は水をきれいにし、海のゆりかごをつくります。そんな回復的(リジェネラティブ)な食材に光を当てます。 - 文化の現場から社会インフラを動かす
家での食事だけでなく、美術館や大学のカフェなど公共の食空間を変えることで、より多くの人に届き、ゆるやかに社会の標準を変えていくアプローチです。
4) 海外での報道・反響
イギリスの主要紙やアート媒体、大学の公式発表などが、展示やネットワークの始動、受賞や会議などを継続的に伝えています。テートの「養殖サーモンの恒久的な提供中止」発表は象徴的で、多くの媒体が取り上げました。こうした報道は「アートの話題」にとどまらず、「食の転換」「海の再生」「文化施設の責任」へと話が広がっています。
日本の状況:報道はほぼ無し
日本語で「Climavore」や「Becoming CLIMAVORE」を調べても、詳しい紹介や継続報道はほとんど見当たりません。
海の高水温化、海藻の減少、漁業の変化といった個別テーマは日本でも報じられていますが、「食の選び方を変え、公共の食空間を動かし、海や土を回復する」という統合的な枠組みとしては、まだ紹介が限られています。結果として、海外では「文化施設のメニューを変える運動」として見えるのに対し、日本では「環境ニュース」や「食のトピック」に分散してしまい、全体像が伝わりにくいのが現状です。
考察編:なぜ日本で広まりにくいのか、どうすれば良いのか
1) 広まりにくい理由(考えられる要因)
- 分野横断のむずかしさ
アート、食、海や農の科学、地域政策などが同時に関わるため、どの担当面からも拾いにくい。 - 実践の場が見えにくい
日本にも環境保全や地産地消の活動は多数ありますが、「文化施設の食を変える」という明確な入口がまだ少ない。動きが点在して見えます。 - 言語と文化の距離
海外の事例は英語情報が中心で、日本語の体系的な一次情報が乏しい。
2) それでも、ここから始められる
- まず公共の食空間を変える
美術館、科学館、大学、図書館など、地域の人が集まる場のカフェや食堂から始めるのが効果的です。メニューに「海をきれいにする食材」「土を肥やす食材」を増やし、なぜそれを選んだかをわかりやすく掲示するだけでも学びの場になります。 - 地域の生産者・研究者・シェフと組む
海藻、貝、在来野菜など、回復的な食材の供給とレシピ開発を、地元と一緒に進めます。 - 物語で伝える
たとえば「満ち引きで現れるテーブル」のように、体で感じられる体験を用意する。難しい専門用語より、見て・食べて・納得できる仕立てに。 - 測り、見える化する
置き換えたメニューで、海や土にどんな良い変化を生むのか。簡単な指標でもよいので効果を記録し、公開します。
まとめ
Climavoreは、「何を食べるか」ではなく「食で、何を回復させるか」という視点をくれます。海外では文化施設を起点に、メニューを着実に変える取り組みが進み、報道も積み上がっています。日本ではまだ紹介が少ないからこそ、最初の一歩をつくる価値があります。
美術館や大学のカフェ、自治体の食堂、観光拠点のレストランなど、公共の食の現場から始める——その積み重ねが、海や土や生きものへの小さくて大きな投資になります。
参照URL
- CLIMAVORE 公式「Becoming CLIMAVORE」概要
https://www.climavore.org/becoming-climavore - Cooking Sections「Becoming CLIMAVORE」プロジェクト(21館が養殖サーモンを外した記録)
https://www.cooking-sections.com/Becoming-CLIMAVORE - 「You can taste CLIMAVORE at」(参加文化施設リスト:V&A、BFI Southbank、テート各館、サイエンスミュージアム等)
https://becoming.climavore.org/p/you-can-taste-climavore-at - Serpentine(ロンドン)プレス・ページ(文化施設でのメニュー転換)
https://www.serpentinegalleries.org/about/press/becoming-climavore/ - The Holburne Museum(ベンugoと連携しメニュー開発の記述あり)
https://holburne.org/becoming-climavore/ - The Caterer(Benugo と Cooking Sections の協働・参加館の具体例)
https://www.thecaterer.com/news/benugo-collaborating-turner-prize-cooking-sections-becoming-climavore-art-make-dishes-more-sustainable - Barbican プレス資料(Benugo との「Becoming CLIMAVORE x Benugo」)
https://www.barbican.org.uk/sites/default/files/documents/2022-03/Our%20Time%20on%20Earth%20-%20Press%20Release%20-%20March%202022.pdf - テートの発表(養殖サーモンを恒久的に外した旨の言及)
https://www.tate.org.uk/press/press-releases/art-now-cooking-sections-salmon-red-herring-0 - RCA(Royal College of Art)公式:CLIMAVORE x Jameel at RCA
https://www.rca.ac.uk/research-innovation/research-centres/climavore-x-jameel-at-rca/ - CLIMAVORE x Jameel(公式サイト側の解説)
https://www.climavore.org/climavore-jameel-at-rca - Community Jameel(ローマでの「CLIMAVORE Assembly」などの記録)
https://www.communityjameel.org/news/the-first-climavore-assembly-takes-place-in-rome-28-29-october-2023 - MAPS(デンマーク、2025年1月にネットワーク参加)
https://mapsmuseum.com/en/about/becoming-climavore-uk/ - Skye/Raasayでの地域連携(養殖サーモンからの転換と10店舗の置換)
https://cooking-sections.com/filter/alon-schwabe/CLIMAVORE-On-Tidal-Zones